2008年10月25日
原小学校耐震工事 現場状況(その6)
皆さん、こんにちは 。
。
ともたかです 。
。
前々回に鉄骨ブレースの設置の事をアップしました。

このように・・・・ 。
。
これには、まだ続きがありました・・・・・・ 。
。
ので、その続きのことを書いてみます。
鉄骨ブレースは、設置して終わりなのではなく、このあとコンクリートの打設があります 。
。
どこに打設するのかというと・・・・・・・。
上の写真をよく見ると、ブレースの廻りに隙間がありますね。
この隙間を埋めるわけです 。
。
施工方法は、特別難しいものではなく、隙間を型枠でふさいでいきます 。
。


隙間を塞いだら、コンクリートを流し込みます・・・・・・ 。
。
ここで使用するコンクリートは、無収縮モルタル(建築では、グラウトとよびます。)というものを使用します。
さらにそのモルタル(グラウト)も水との配合が適切かどうか検査をしてから打設をしていきます。
作業の流れは・・・・・・・。
まず
 。
。
適正な材料が搬入されているか確認をします 。
。

これらが、試験道具です 。
。

立会いの下、試験をして、適正な配合かどうかを検査します 。
。

この試験により、設計通りに打設できるかを判断し、合格すると打設移ります 。
。
通常、セメントはプラントと呼ばれる製造工場から出荷されますが、耐震工事で使用するモルタル(グラウト)は、
現場でセメントを練ることが多いです。

小型のポンプにてモルタル(グラウト)を圧送して型枠内に充填しいきます 。
。

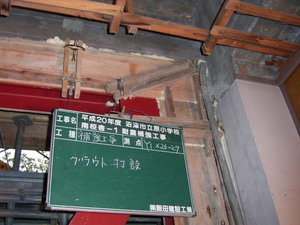
中のモルタル(グラウト)が固まり、型枠を外すと・・・・・・ 。
。

どうです? きれいに隙間が埋まっているでしょう 。
。
これで、ブレースの設置完了となるわけです 。
。
ここまでできると、メインとなる補強工事自体は完了となります。
ここから先は、内装、外装の工事に移っていくわけです・・・・。
次回もお楽しみに・・・・・・・
 。
。ともたかです
 。
。前々回に鉄骨ブレースの設置の事をアップしました。
このように・・・・
 。
。これには、まだ続きがありました・・・・・・
 。
。ので、その続きのことを書いてみます。
鉄骨ブレースは、設置して終わりなのではなく、このあとコンクリートの打設があります
 。
。どこに打設するのかというと・・・・・・・。
上の写真をよく見ると、ブレースの廻りに隙間がありますね。
この隙間を埋めるわけです
 。
。施工方法は、特別難しいものではなく、隙間を型枠でふさいでいきます
 。
。隙間を塞いだら、コンクリートを流し込みます・・・・・・
 。
。ここで使用するコンクリートは、無収縮モルタル(建築では、グラウトとよびます。)というものを使用します。
さらにそのモルタル(グラウト)も水との配合が適切かどうか検査をしてから打設をしていきます。
作業の流れは・・・・・・・。
まず

 。
。適正な材料が搬入されているか確認をします
 。
。これらが、試験道具です
 。
。立会いの下、試験をして、適正な配合かどうかを検査します
 。
。この試験により、設計通りに打設できるかを判断し、合格すると打設移ります
 。
。通常、セメントはプラントと呼ばれる製造工場から出荷されますが、耐震工事で使用するモルタル(グラウト)は、
現場でセメントを練ることが多いです。
小型のポンプにてモルタル(グラウト)を圧送して型枠内に充填しいきます
 。
。中のモルタル(グラウト)が固まり、型枠を外すと・・・・・・
 。
。どうです? きれいに隙間が埋まっているでしょう
 。
。これで、ブレースの設置完了となるわけです
 。
。ここまでできると、メインとなる補強工事自体は完了となります。
ここから先は、内装、外装の工事に移っていくわけです・・・・。
次回もお楽しみに・・・・・・・




